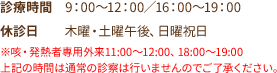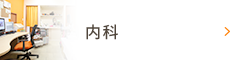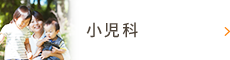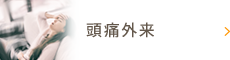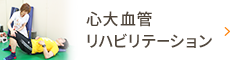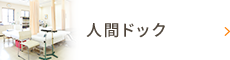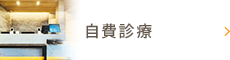糖尿病外来

糖尿病は、膵臓から分泌されるホルモン「インスリン」の分泌不足・作用不足がもたらす疾患です。
インスリンは血糖値をコントロールする唯一のホルモンで、膵臓・ランゲルハンス島のβ(ベータ)細胞でつくられます。食後など、血糖値が上がると速やかに必要量が分泌されますが、何らかの原因でこの仕組みがうまく働かなくなると、血中のブドウ糖が細胞内へ取り込まれず、高血糖状態が続いてしまいます。
高血糖状態が続くと尿中に糖が排泄されるほか、心筋梗塞・脳梗塞・腎症・神経障害など命に関わる合併症のリスクが高まります。
初期にはほとんど自覚症状がなく、健康診断で血糖値やHbA1c(過去1~2か月の血糖値平均を表す指標)が指摘されても放置してしまう方も少なくありません。
しかし早期に受診し、食事・運動療法をはじめ、内服薬やインスリン療法を適切に組み合わせ合併症の進行を抑えることが健康維持に繋がります。
当院の糖尿病外来では、詳細な問診と検査(血糖値・HbA1c・尿検査など)に基づき、患者さま一人ひとりのライフスタイルや合併症リスクに合わせた治療プランをご提案します。お気軽にご相談ください。
糖尿病の種類
糖尿病は大きく「1型糖尿病」「2型糖尿病」「妊娠糖尿病」「その他の特定の機序や疾患による糖尿病」の4つに分類されます。
〈1型糖尿病〉
1型糖尿病は主に小児から青年期にかけて発症し、自己免疫によって起こる糖尿病です。
自分の体が自分のβ細胞を攻撃する抗体を作ってしまうことでβ細胞が破壊され、インスリンが分泌されなくなります。そのためインスリン注射を打って血糖コントロールを行う必要があります。
発症する原因は正確にはわかっていませんが、遺伝的要因やウイルス感染をきっかけにβ細胞への自己免疫反応が生じているとも言われています。1型糖尿病の患者さんは糖尿病患者さんの5%ほどです。
症状として、食べているのに痩せる、体がだるい、多飲多尿、口の渇きなどがあげられます。
〈2型糖尿病〉
2型糖尿病はインスリン分泌量の低下、インスリンが効果を発揮しきれない「インスリン抵抗性」によって発症します。
40歳をすぎてから発症することが多く、肥満や運動不足・食べ過ぎといった生活習慣に、遺伝的な要素も組み合わさって引き起こされます。
初期症状はほとんどないため気付かないうちに進行し、気づいたときにはすでに悪化してしまっているというケースが多いです。
治療の基本は「食事・運動・薬」の3つです。
・食事療法
目標体重を設定し摂取エネルギーを適正範囲におさえ、体重管理をしていきます。糖質・脂質・タンパク質をバランスよく摂り、間食や飲酒習慣があれば改善していきます。
食事療法だけでもインスリン分泌量が改善されることは多く、薬物療法を行っている方でも、お薬の量を減らすことが可能です。

・運動療法
運動は特に有酸素運動が推奨されています。
ジョギングや散歩など、ゆっくりと深く呼吸をしながら体を動かしていきましょう。
筋肉に負荷をかける無酸素運動も週に2~3回組み合わせて行うことで、より効果的です。また、毎日の生活のなかで座る時間を短くし、適宜軽く体を動かすことを意識することも重要です。

・薬物療法
食事療法、運動療法でも改善がみられない場合は、注射薬や内服薬を用いて治療を行います。
経口血糖降下薬のほか、インスリン注射や膵臓からのインスリン分泌量を増やすGLP-1受容体作動薬の注射などさまざまな種類があります。
当院では患者さんの年齢・既往歴・生活習慣などを考慮し、お一人おひとりにあったお薬を提供します。副作用の説明や、食事療法・運動療法のアドバイスなど総合的なサポートをおこないます。

妊娠糖尿病
妊娠中に発症する一時的な糖尿病で、妊娠するまでは判明していなかったり、糖尿病に進行していない程度まで血糖値が上がる状態です。
妊娠中のホルモンの変化によって引き起こされ、インスリンの効果を弱くするホルモン(ルチゾールやプロラクチン、プロゲステロンなど)が増加する影響を受け、インスリンの効果が低下します。
過剰に糖を減らすと成長に支障をきたすことがあるため、お腹の赤ちゃんにしっかりと栄養を届けつつ、血糖コントロールをする必要があります。
妊娠が終われば元通りになる場合が多いですが、妊娠糖尿病を経験した方は2型糖尿病発症のリスクが高まる場合があります。また、妊娠糖尿病は自覚症状がほとんどないため、妊婦健診を適切に受けることが大切です。
・食事療法
目軽症であれば食事のコントロールで血糖値を安定させることが可能です。適切なエネルギー量とバランスのとれた食事を心がけましょう。

・運動療法
軽症であれば食事のコントロールで血糖値を安定させることが可能です。適切なエネルギー量とバランスのとれた食事を心がけましょう。

・薬物療法
血糖モニタリングで数値を確認し、食事療法や運動療法で改善がみられない場合はインスリン注射を行うこともあります。

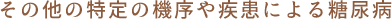
糖尿病は上記以外にも、遺伝子異常や膵炎や膵がんなどの病気、血糖値が上がるお薬の副作用が原因で発症する場合もあります。